〒673-0893 兵庫県明石市材木町16番15号
受付時間
定休日:土曜・日曜・祝日
(事前に予約をいただいた場合は面談可能)
相続人が亡くなった家族の遺言書を見つけた場合
はじめに
こんにちは。司法書士の荻野です。
相続があった場合、遺言書を保管していた人や遺言書を発見した相続人がしないといけないこと、逆にしてはいけないことがあるのをご存じですか?
このページでは、遺言書を保管していた人や遺言書を発見した相続人の対応について説明しています。
1.相続人や保管者がしなければいけないこと
遺言書を発見した場合、家庭裁判所で遺言書の検認という手続きをしてもらう必要があります。
公正証書遺言・法務局に保管されていた遺言書は検認が不要です。
※公正遺言についての詳しい説明はこちらをご覧ください。
この検認とは、家庭裁判所が、遺言書の形状や加除訂正の状態、日付、署名など検認日の遺言書の内容を明確にして、遺言の偽造・変造を防止する手続きです。
検認手続きは、遺言の偽造・変造の防止を目的としているため、遺言書の有効・無効を判断わけではありません。

2.どこに検認の申立てをするの
遺言書を保管していた人や遺言書を発見した相続人は、遺言者の最後の住所地にある家庭裁判所に遺言書の検認を請求します。
3.保管者や相続人がしてはいけないこと
保管や発見した遺言書に封印がされていた場合には要注意です。
遺言書を作成した人が亡くなってもすぐ遺言書を開封をしないでください。
家庭裁判所外で封印のある遺言書を開封した者は、5万円以下の過料に処せられてしまします。
封印のある遺言書は、家庭裁判所で相続人、相続人の代理人の立会いがないと開封できないとされており、
検認の手続きで開封されることになります。
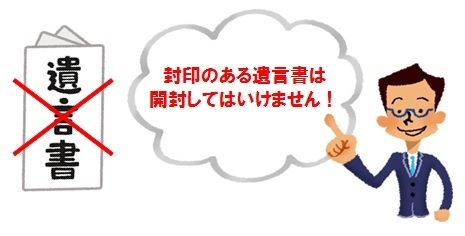
4.検認の流れ
検認の申立てがあった場合、家庭裁判所は相続人に検認日を通知します。
検認日に出席するかは任意となり、全員の出席がなくても検認手続きは行われます。
検認の日に、申立人が家庭裁判所に遺言書を提出し、裁判官は、出席した相続人立会いのもと、遺言書を開封し、検認を行います。
そして検認後に、検認済証明書を申請し、遺言書に検認済証明書を付けてもらいます。
不動産・預貯金・株式等、検認手続きが済んでいないと相続手続きで、
名義変更ができないものが多く、遺言書の執行をするためには遺言書の検認は必要です。
いかがでしょうか。
このページが、皆さまのお悩みの解決に繋がれば幸いです。
明石市の司法書士 荻野司法書士事務所

「困っているけど、話を聞いてみないと依頼するか分からない」
「こんなこと相談してよいのか」とお悩みの方
ご依頼前の相談は無料ですので、お気軽にご相談ください。
| 受付時間 | 9:00~18:00 |
|---|
| 定休日 | 土曜・日曜・祝日 (事前に予約をいただいた場合は面談可能) |
|---|



